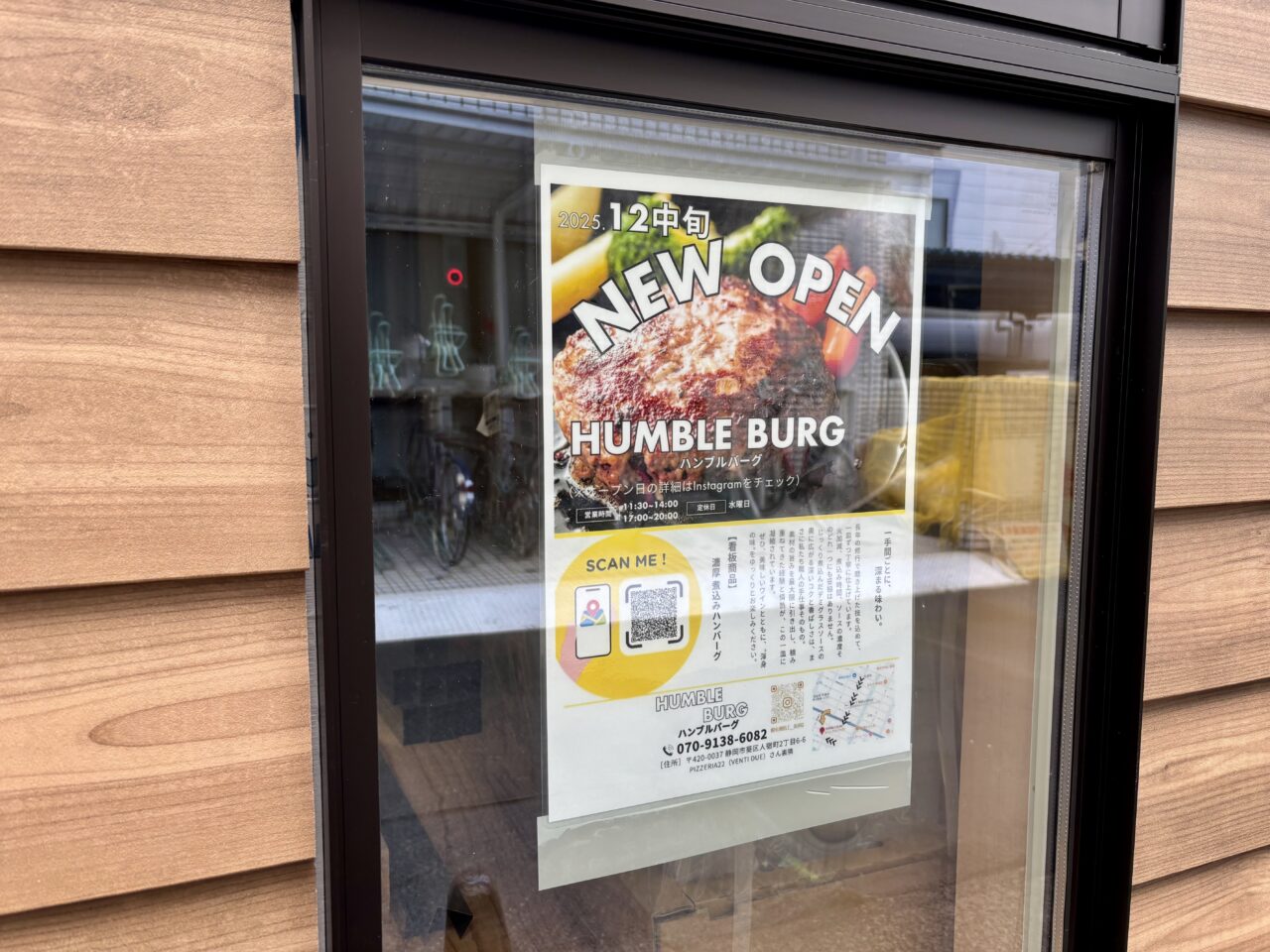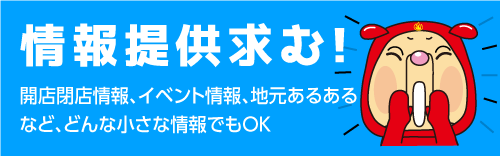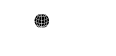【静岡市葵区】4月1日(火)~5日(土) 、静岡浅間神社廿日会祭と駿府の春を彩る伝統行事「お踟(おねり)」。
静岡市の春を告げる伝統行事「お踟(おねり)」。この行事を守り伝えるために発足したのが 駿府踟振興会 です。「お踟」は、2025年4月1日(火)~5日(土) にかけて行われ、
華やかな山車(だし)や神輿(みこし)が駿府の街を練り歩きます。毎年4月1日から5日、桜が満開に咲き誇る中で行われ、特に 5日の15時半からは「国指定重要無形民俗文化財」の「稚児舞楽」 が奉納されることで知られています。この時期の静岡市街地は、色とりどりの山車や賑やかな屋台が繰り出し、訪れる人々で大いに活気づきます。


※写真はイメージです
「お踟」の起源
「お踟」の歴史は古く、今川時代 にまでさかのぼります。
旧暦2月20日に行われる 廿日会祭(はつかえさい) に由来し、
もともとは 天下泰平や五穀豊穣を祈願 する行事でした。
一時衰退しましたが、徳川家康公が駿府在城の際に復興 させたと伝えられています。
その後、明治時代や昭和時代にも中断と再興を繰り返しながら、
平成5年には静岡市連合町内会が「駿府踟振興会」を立ち上げ、
この貴重な文化を守り続けています。
「お踟」の見どころ
祭りの期間中、市街地を練り歩くのは 5台の山車 と 神輿 です。
【現在の山車】
神武車(じんむぐるま)
暫車(しばらくぐるま)
稲荷車(いなりくるま)
木花車(このはなぐるま)
咲耶車(さくやぐるま)


※写真はイメージです
山車の引き回しに加え、木遣り(きやり)やお囃子(おはやし)、地踊り(じおどり) なども披露され、
まさに江戸時代のような賑わいが広がります。
「お踟」の意味とは?
「お踟(おねり)」とは、祭礼の行列が ゆったりと練り歩く 様子を指します。
辞書では「お練り」と表記されることが多いですが、
駿府では 「踟」と書き、「町中をねって足で知る」 という意味が込められています。
この春、静岡の歴史と文化を感じながら、街を巡る「お踟」をぜひ体感してみてください。
静岡浅間神社はこちら↓